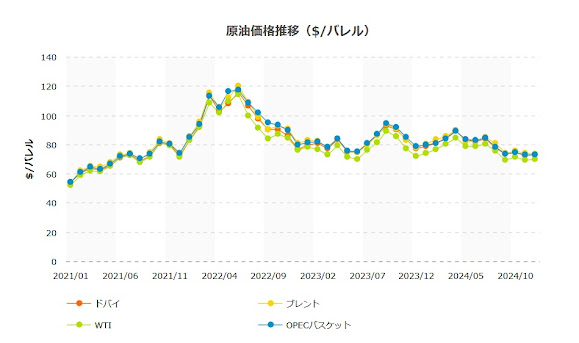週刊文春は「訂正」を出す必要などなかった。
< <中居正広・フジテレビ問題に関して、週刊文春が「訂正」を出した。「フジ社員の関与」の有無について誤りがあったというのだが、該当記事を丁寧に読むと、訂正を出すようなものではないと分かる> 中居正広・フジテレビ問題に関して週刊文春は28日、記事内容に誤りがあったとして「訂正」を出した。重要ポイントの一つであった「フジ社員の関与」の度合いが大きく後退し、SNSやワイドショーでは文春への非難が相次いだ。 私もこの場を借りて、文春の対応を強く批判したいと思う。それは、誤報を出したからではない。誤報ではないにも関わらず、訂正を出したからだ。文春は訂正を出す必要などなかった。以下、説明する。 決して断定はしていない まず、文春が発表した訂正文を確認すると、このように書かれている(<>内は引用部分)。 <【訂正】本記事(12月26日発売号掲載)では事件当日の会食について「X子さんはフジ編成幹部A氏に誘われた」としていましたが、その後の取材により「X子さんは中居に誘われた」「A氏がセッティングしている会の"延長"と認識していた」ということがわかりました。お詫びして訂正いたします。また、続報の#2記事(1月8日発売号掲載)以降はその後の取材成果を踏まえた内容を報じています。> 訂正文では<『X子さんはフジ編成幹部A氏に誘われた』としていました>とあるが、該当記事(12月26日発売号掲載の記事)を何度読んでも、そこまで断定的には書かれていない。 記事ではまず、文春に先んじて第一報を報じた『女性セブン』を間接的に引用し、こう書いた。 <記事によると、2023年にX子さんは中居、フジテレビの編成幹部A氏と3人で会食する予定だったが、A氏がドタキャン。彼女と中居は2人で会食することになったが、そこでトラブルが発生。> トラブルが起きた日の出来事を記しているが、ここでは会食について「A氏がX子さんを誘った」とは書かれていない。誰がX子さんを誘ったかは、これを読んだだけでは分からない。 別の段落では、X子さんの知人がこう証言している。 <「あの日、X子は中居さん、A氏を含めた大人数で食事をしようと誘われていました。多忙な日々に疲弊していた彼女は乗り気ではなかったのですが、『Aさんに言われたからには断れないよね』と、参加することにしたのです」> <「飲み会の直前に...