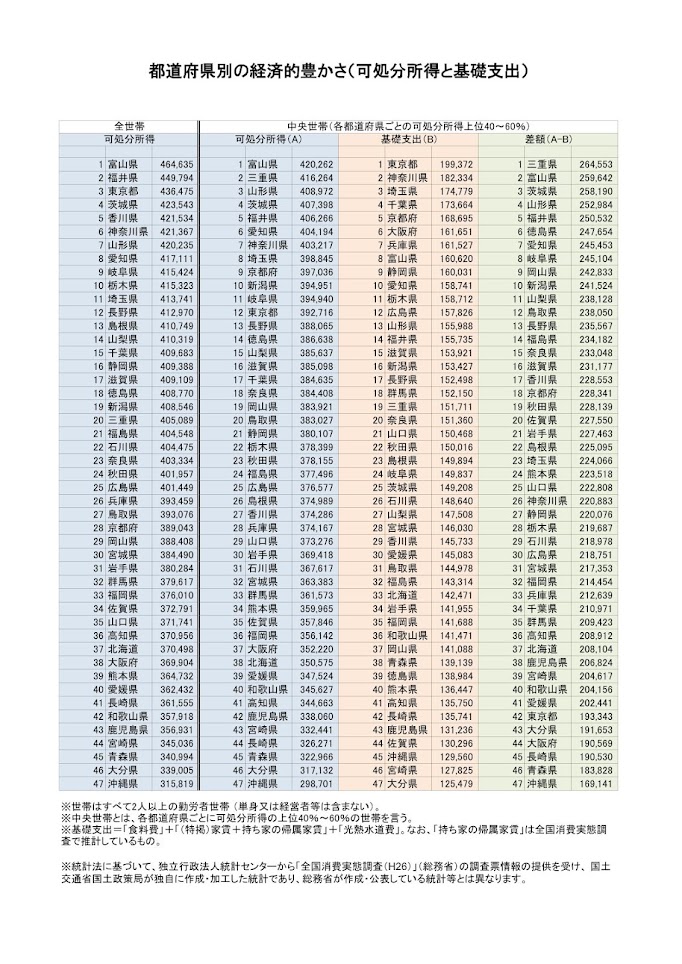皇室に関する事項を国連女性差別撤廃委員会が議論すべき範疇か?
<女性差別撤廃条約の実施状況を審査する国連の女性差別撤廃委員会(CEDAW)は29日、日本政府に対する勧告を含む「最終見解」を公表した。選択的夫婦別姓の導入や、個人通報制度を定めた選択議定書の批准を求めたほか、「男系男子」が皇位を継承することを定める皇室典範の改正を勧告した。 スイス・ジュネーブの国連欧州本部で今月17日、8年ぶりの日本政府の対面審査が行われた。NGOからの情報提供も踏まえ、委員会が最終見解をまとめた。 最終見解では前回2016年の勧告以降の、結婚年齢の格差解消や、女性の再婚禁止期間廃止を実現する法改正などを評価する一方、幅広い分野で改善を勧告した。 委員会は2003年、09年、16年と過去3度、「夫婦同姓」を定める民法改正の必要性を指摘している。17日の審査で委員が「女性のほとんどが夫の姓を名乗っており、アイデンティティーや雇用に悪影響を及ぼしている」と指摘。政府側は「国民の間で意見が分かれている」などとして選択的夫婦別姓の推進方針を明示しなかった。 委員会は最終見解で民法改正を求め、前回16年に続いて、最も重要な「フォローアップ項目」に指定した。 勧告では人権侵害された個人が国内で救済されない場合に国際機関に訴えられる個人通報制度を定める「選択議定書」の批准も求めた。条約の実効性を高める狙いがあり、条約の締約国189カ国のうち115カ国が批准している。 また、中絶に配偶者の同意が必要だとしている母体保護法の要件削除を求めた。審査で委員は「日本が近代国家、経済大国であることを考えると驚くべきことだ」と述べていた。 「男系男子」が皇位を継承することを定める皇室典範についても、最終見解は「委員会の権限の範囲外であるとする締約国の立場に留意する」としつつ、「男系の男子のみの皇位継承を認めることは、条約の目的や趣旨に反すると考える」と指摘。「皇位継承における男女平等を保障するため」、他国の事例を参照しながら改正するよう勧告した。政府側は17日の審査で、「皇位継承のあり方は国家の基本に関わる事項であり、女性差別撤廃条約に照らし、取り上げることは適当でない」と反論していた。 このほか、最終見解は性的少数者の人権をめぐり、同性婚を認めること、昨秋の最高裁判決で違憲・無効となった性同一性障害特例法の生殖不能要件のもと不妊手術を受けた人への賠償を要請...