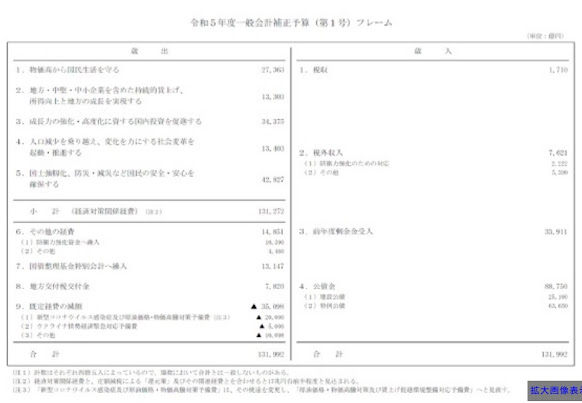連合オバチャンの視野に労働者は存在するのか。
< 政権ベッタリ。連合の芳野友子会長が理解できぬ対話と癒着の違い みなさま、こんにちは! 「衰退ニッポンの暗黒地図」をお届けするマネーアナリストの神樹兵輔(かみき・へいすけ)です。 読者の皆様は、「れんごう」という言葉を耳にして、何を思い浮かべるでしょうか。 板紙・段ボール製造の国内最大手の 「レンゴー(株)」でしょうか、それとも自民党とべったり癒着関係の旧統一教会の現在の名称「世界平和統一家庭連合」のことでしょうか。 あるいは、もっと巨視的に見て、世界各国が連なる「国際連合」や「欧州連合(EU)」のことだったりするでしょうか。 それとも、政治献金を自民党にだけバラ撒いて、政策を自分たちの都合のいいようにコントロールしてきた「経団連」という略称で呼ばれることの多い「日本経済団体連合会」のほうでしょうか。 いずれにしても、近年「れんごう」と聞いて、肝心の「日本労働組合総連合会」のことを最初に頭に思い浮かべる人は、まずいないのです。 つまり、近年は労働団体の地盤沈下が著しいため、「連合」と聞いても、「何のこっちゃ?」という状況のわけです。 これが、労働運動の地位が極度に低下した日本における労働組合のナショナルセンター(全国中央組織)の「日本労働組合総連合会」の象徴ともいうべき状況です。 賃上げのためのストライキもすっかり封印してしまった、労使協調第一主義の日本の労働組合の中央組織は、なぜ、こんなに落ち目になってしまったのでしょうか。 今回のテーマは、その「連合(日本労働組合総連合会)」について、その体たらくぶりを、いろいろえぐっていきたいと思います。 日本の労働組合が大同団結で結集し、構成された「連合」は、かつては、新聞やマスメディアのニュースで取り上げられることも多かっただけに、「れんごう」といえば、「日本労働組合総連合会」を指すのが一般的であり、「連合」は700万人弱もの労働組合員数 を有する日本最大の団体であり、その代表的存在だったはずなのです。 そんな数の力をさえ活かせないのが今の「連合」です。 もはや、というべきか、やはり、というべきか、近年はすっかりショボイ存在になり下がっているのが「連合」なのです。 単純に総括してしまうと、かつて「連合」という名称で誰もが想起していた「日本労働組合総連合会」は、存在自体が低下したため、いまや表向...