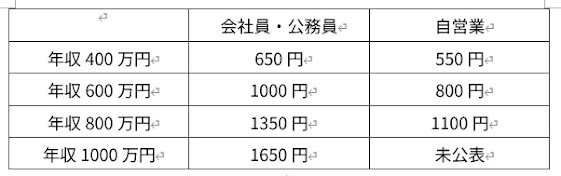中国製の電子機器に搭載されている半導体は二年前の7nmのままだ。
<・「MateBook Fold」、2年前と同じ7ナノのプロセッサー使用 ・台湾TSMCは年内に3世代先の2ナノを量産見通し 中国の華為技術(ファーウェイ)の最新パソコン(PC)が、数年前と同じ半導体を搭載していることが分かった。米国の制裁が中国の最先端半導体の開発を妨げているとみられる。 カナダの調査会社テックインサイツによると、「MateBook Fold」に搭載されたプロセッサーは、中芯国際集成電路製造(SMIC)が有する回路線幅7ナノメートル(ナノは10億分の1)の技術で製造されている。これは、2年前に米当局を驚かせたファーウェイのスマートフォン「Mate 60 Pro」と同じ技術だ。それ以降は半導体の性能向上の取り組みがほとんど前進していないことを示唆している。 MateBook Foldはファーウェイが5月に発表した新型の折りたたみPC。タブレットとしても使えるハイブリッド型で、同社が独自開発した基本ソフト「HarmonyOS」を搭載している。同社は中国政府の方針に従って自社の技術や部品の開発を進め、アップルやマイクロソフトなどの企業に対抗しようとしているが苦境が続いている。 米国が主導する多国間の制裁によって中国は欧米の先端製造装置や技術へのアクセスが遮断されている。例えばオランダの半導体製造装置メーカー、ASMLホールディングは、高性能な人工知能(AI)半導体の製造に必要な最先端のリソグラフィ装置を中国企業に販売することを禁止されている。 また、業界最大手の台湾積体電路製造(TSMC)は、今年後半に7ナノメートルより3世代先の2ナノメートルの半導体チップを量産する見通しとなっている。 米商務省のケスラー次官は今月開かれた米議会の公聴会で、輸出規制によってファーウェイが2025年に製造できる人工知能(AI)半導体「Ascend(アセンド)」は20万個程度にとどまると発言している>(以上「Bloomberg」より引用) 米国の対中半導体規制が効いているようだ。「 ファーウェイ最新PC、数年前と同じ半導体搭載-米の対中制裁が影響 」との見出しが米紙を飾った。 一時、中国企業DeepSeek(ディープシーク)が発表した最新Aが世界のハイテク業界と金融市場に大きなインパクトをもたらした。その性能は米オープンAIなどが開発した最先端の大規模...