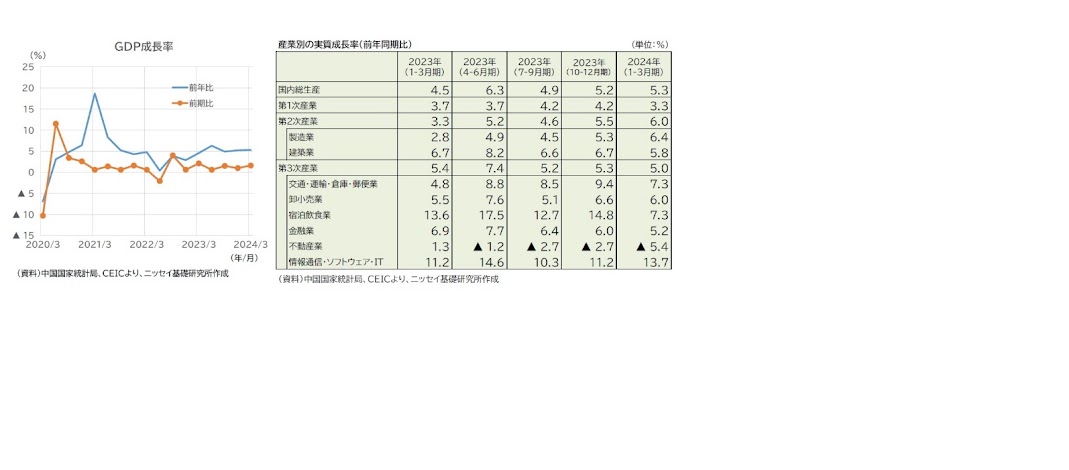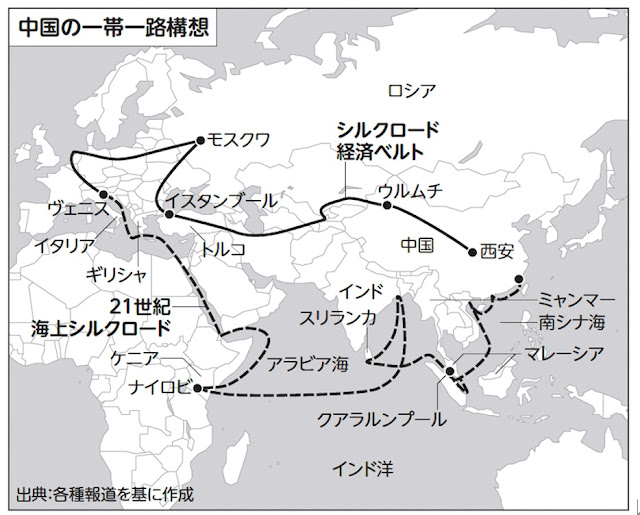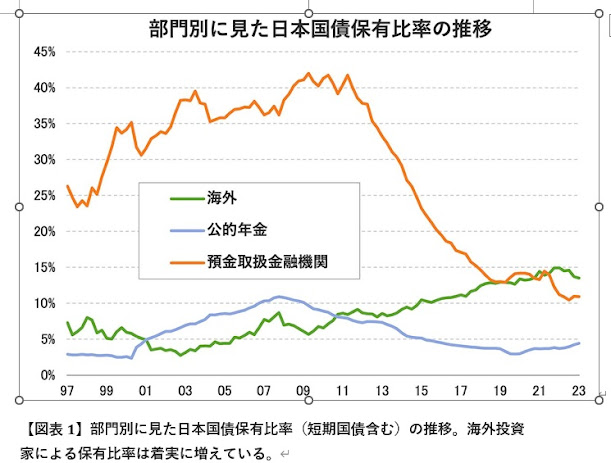中国製EVの脅威を、日本は殆ど恐れる必要はない。
< 中国“EV大国”にほころび? 「デフレ輸出」が新たな脅威に 「自動車強国」という目標を掲げ、国を挙げてEV=電気自動車へのシフトを進めてきた中国。 斬新なデザインの新型EVが次々登場しています。 その市場に今、変調の兆しが見え始めています。EVの販売の伸びが鈍化しているのです。 「EV大国」の“ほころび”ともみえる現象が国のあちこちで顕在化。メーカーの間では値下げ競争が激しさを増し、価格の安いEVを外国で販売する「デフレ輸出」の脅威が世界に及び始めています。 操業停止に追い込まれた新興EVメーカー 北京中心部にあるEVの販売店を2024年2月に訪れると、店の扉には大きな南京錠がかかっていました。 ガラス張りの店内をのぞくと、接客用のテーブルには飲みかけのペットボトルが放置され、ゴミ箱はふたがあいたまま。さながら夜逃げしたかのような状態になっていました。ここは中国の新興EVブランド「ハイファイ」の店舗です。 このブランドは斬新なデザインと高性能かつ高級感あふれるインテリアで多くの顧客の心をとらえ、1000万円前後の高級EVメーカーとして広く知られた存在でした。 しかし、2月に操業停止に追い込まれたのです。近くにある別のメーカーの販売店の関係者は、「あの店舗は2月初めに営業を停止した。資金繰りが悪化したようだ」と話していました。 5月に入って、ハイファイが香港の投資機関などから融資を受けたのではないかなどと一部の中国ネットメディアが報じましたが、2月に取材した販売店を訪れると、ハイファイの名前は取り外され、もぬけの殻。 2月時点ではまだEVを展示していた別の店舗も今は他メーカーの販売店に変わっていて、先行きは不透明なままです。 中国のネットメディアは「2024年は血みどろの競争、淘汰の嵐がやってくる」と論評し、100以上あるとされるEVブランドで、「真に生き残れるのは5社だ」と語る複数のメーカー幹部の声を伝えています。 EV大国に異変? 中国政府はこれまでEVシフトを強力に推し進めてきました。補助金を拠出し、販売を促進。 EVシフトによって、ガソリン車では対抗できなかった欧米メーカーを追い越し、世界市場をリードする「自動車強国」を目指そうという習近平国家主席の強い意志を実行に移してきたのです。この結果、EVの販売台数は拡大の一途を辿りました。202...